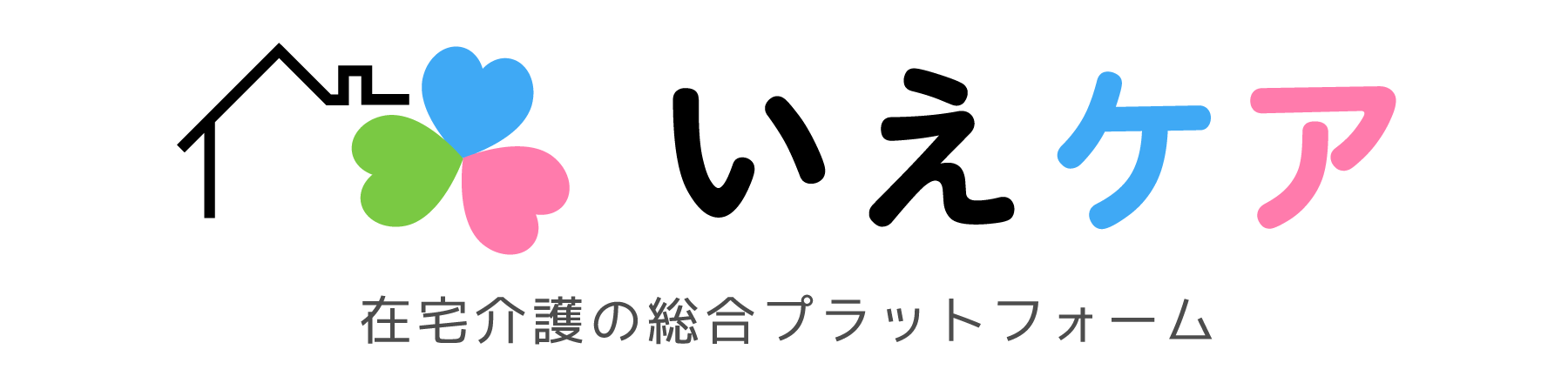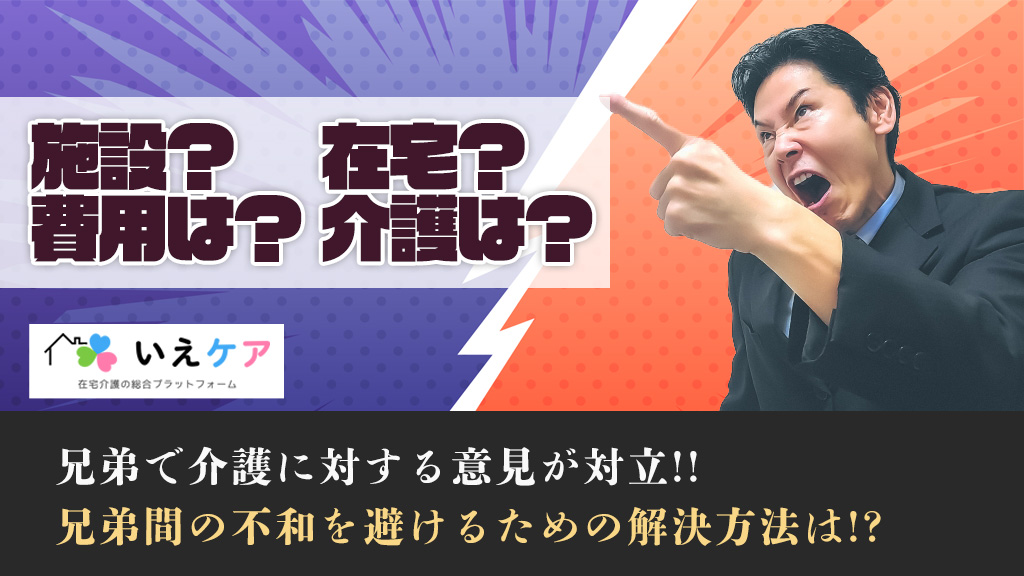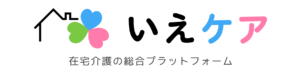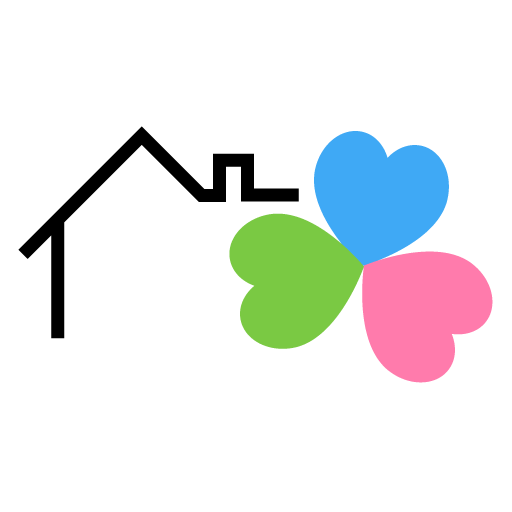
いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
ユーザーの方から届いた質問に介決サポーターがお答えします。
今回の質問は介護をめぐって意見が異なる家族に関するものです。
人それぞれ、介護に対する考え方は異なります。たとえ親しい兄弟や夫婦であっても、考え方は違います。施設に入所すべきか、在宅で生活すべきか、介護は誰がするべきか、費用はどうするか。介護に関する方針で対立・トラブルになることも少なくありません。
今回は兄弟間での介護トラブルを避けるためのポイントを解説します。
質問「兄弟で介護に対する意見が対立」
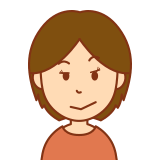
義母の介護のことで相談します。
現在、義母は隣町に一人で暮らしています。私は義母から見て次男の嫁になります。
義母はもともと膝が悪く、外出もままならなかったのですが、最近ではアルツハイマー型の認知症になり、訪問介護サービスを利用しながら一人暮らしをしています。
夫も時々義母のところに行って、通院の付き添いや買い物などを協力して、なんとか生活を成り立たせています。
夫には6つ上の兄がいるのですが、義兄は「火事でも起こしたら大変だからすぐにでも施設に入れるべきだ」と言います。介護度がまだ要介護1のため、特別養護老人ホームには入れないということなので、入るとしたら有料老人ホームだと思うのですが、高額な費用が心配です。
入居費用は母の年金と、足りない分は兄弟で折半するという義兄からの提案だったのですが、まだ私たち夫婦は子供2人が大学生、住宅ローンもあり、恥ずかしい話ですが十分な貯蓄もありません。逆に義兄はすでに子供も社会人となり、ローンも完済しているようなので、お金の面でも余裕があるようです。施設入所が長期間になれば私たちの経済面の不安もあります。
私と夫は、義母の生活の様子を普段から見ておりますが、サービスを利用することでまだ自宅で十分生活できるように感じています。遠方に住んでいる義兄は介護にはほとんど協力していないのに、自分が長男だからと自分の意見を押し通したいように感じます。
兄弟間で施設か自宅かという意見で対立しています。もともとは仲の良い兄弟だったのですが、介護がきっかけで兄弟間の不和につながっています。このような介護に関する方針の違いをどのように解決していけばいいのでしょうか。教えてください。
―――という質問でした。
では、在宅介護の強い味方「介決サポーター」からのアドバイスをお願いします。
介決サポーターがお答えします!

ご相談ありがとうございます。
兄弟で介護に関する方針が対立してしまい、解決する方法がないか困っているということですね。自分たちは義母の通院の付き添いや買い物などをして在宅生活の維持のために協力しているのに、義兄は簡単に「施設に」と言う。住宅ローンや子供の学費などで大変な中、施設という決断は経済的にも不安ですよね。お悩みになられる気持ち、よくわかります。
今回の質問者様と同じように、家族間で意見が食い違い、対立を生んでしまうことがあります。兄弟間の意見の相違が、最終的には法律トラブルに発展してしまう事例もあります。
それぞれの立場・経済状況・介護観などの違いにより、意見が異なることはよくあります。では、このような意見・方針の違いをどのようにまとめていくべきなのか、これからお伝えする内容が解決のためのヒントになればと思います。
家族間・兄弟間・夫婦間の介護トラブル

介護をめぐる家族間のトラブルは少なくありません。むしろ、家族全員が同じ意見で一致することの方が珍しいのかもしれません。
家族全員が、同じように状況を把握していて、同じだけの介護を分担していて、同じ費用負担をしているという状況などはあり得ません。介護をすることへの負担感や不公平感を感じ、積み重なった不満が家族間の対立・トラブルに発展します。
家族間のトラブルを生む要因として、以下のようなものあります。
【古い価値観】
「お前は長男の嫁だから介護はお前がやるのが当然だ」という古い認識を持っている方も多くいます。介護をたった一人で担うということは大きな負担と責任が伴います。家族で協力・分担することが必要です。
【何もしないのに口だけ出す】
普段何もしないのに、口だけ出そうとする家族もいます。「昔はこうだった」「こうするのが常識」と自分の意見を押し付けようとするのに、自分では理由をつけて何の介護もしないという家族もいるのです。
【費用負担に協力しない】
介護にはお金がかかります。きれいごとだけでは済まない問題です。親の年金や資産だけで解決できる問題であれば別ですが、そうでない場合、どのように負担しあうかでトラブルになる場合もあります。
【相続問題】
お金があったとしても、また別の問題があります。それが相続問題です。介護には何も協力しないし、お金も負担しなかったのに、他の家族と同じ分だけ遺産を相続しようとする家族もいます。遺産相続をめぐってトラブルが起こることもあります。
このように、家族間における介護トラブルは例を挙げればきりがありません。
では、このような家族間のトラブルを避けるためにはどうすればいいのでしょうか。
家族での話し合いにおけるポイント
家族間の介護トラブルを避けるためのポイントはどこにあるのでしょうか。重要なポイントを3つ紹介します。
家族間でのトラブルを避けるためのポイントを一つずつ解説します。
不公平感の少ない役割分担

家族間の介護トラブルを生まないひとつ目のポイントは不公平感が少なくなるような役割分担をすることです。
家族にもそれぞれできることが異なります。
例えば兄弟の場合、遠方に住んでいるなどの物理的な距離、仕事の関係で時間的な余裕がない、介護費用を支払えるだけの経済的な余裕がないなど、それぞれに事情が異なります。
逆に言えば、それぞれの立場でできることがあるはずです。
このように、自分にできることを探し、役割分担する仕組みを作ることが大事です。どこからどこまでを介護保険サービスで対応するか、これは誰がサポートするか、などをあらかじめ決めておくことで、不公平感の無い役割分担をすることができます。
それぞれが「できないこと」から話し合うのではなく、まずは「できること」をお互いに話し、足りない部分は介護保険サービスや保険外サービスで補うなど、調整していくことができます。
最初からあまりガチガチに役割を線引きして決めてしまうと、突発的な場面で対応ができなくて困ることもあります。役割を決めても、自分の役割じゃないから何もしない、ではなく協力し合う姿勢も必要です。
家族間の介護トラブルを生まないポイントひとつ目、不公平感の少ない役割分担について解説しました。
中立な第三者を交えて話をする

家族間の介護トラブルを生まないふたつ目のポイントは中立な第三者を交えて話をすることです。
話し合いの場を持つとしても、それぞれが自分の意見を主張するだけでは話もまとまりません。家族での介護の話し合いの方法を間違えることで、かえって対立が深くなる場合もあります。このような場合には中立な第三者を交えて話をすることが必要です。
普段からよく面倒を見てくれている近隣の方や民生委員、担当しているケアマネジャーなど、本人の不断の様子をよく見ている方や、信頼できる方に話し合いの場に同席してもらうことをお勧めします。客観的な視点が入ることで、解決できることもあります。第三者が入ることで感情的な対立が生まれにくく、客観的に話し合いを不公平感なく収めることができます。
また、ケアマネジャーのような専門職であれば、専門的な別の視点からのアドバイスで第3の方法を見つけることもできるかもしれません。もちろんケアマネジャーも多忙ですので、サービス担当者会議や訪問の際に合わせて相談する機会が持てるといいですね。
話し合いでよく起こるトラブルとして、その場で決まった決定事項であっても、「そんなこと言っていない」「そんな話をした覚えはない」と否定されてしまうことがあります。いわゆる言った・言わないという問題です。これも、第三者が入っていることで、話し合いの証人となってくれるため、トラブルが起こりにくくなります。
個人的におすすめの方法としてはライングループなどのチャットツールをケアマネさん交えて行うことです。情報のやり取りが可視化され、言った言わないがなくなります。ケアマネの定期訪問(モニタリング)もオンラインモニタリングが条件付きで許可されており、導入している事業所もあります。
家族間の介護トラブルを生まないポイントふたつ目、中立な第三者を交えて話をすることを解説しました。
本人の意見を尊重する

家族間の介護トラブルを生まないみっつ目のポイントは本人の意見を尊重することです。
介護に関する話し合いでよく起こることは、一番大事な本人の気持ちが無視されてしまうことです。
質問者の相談内容でも、本人の気持ちはどうなのかという視点はありませんでした。介護に関する話し合いは、介護する側の問題でもある一方、介護される本人の人生を決める重要な問題でもあるということです。
本人がどう生きていきたいのか、困ったときに誰を頼りたいのか、誰にそばにいてほしいのか、どこで過ごしたいのか。本人の要望が必ずしもかなえられる状況とは限りませんが、本人の意思を無視するのではなく、本人の意見を出発点に解決策を探していくことが重要です。
たとえ認知症になっていたとしても、どう暮らしていきたいか、自分自身の想いを伝えられる場合も多いです。もしそれができなかったとしても、これまで本人が話してきた希望や、それまでの生活から、本人の思いを推測することも可能です。
最近はあらかじめ自分の希望をエンディングノートとして文字に残しておく方も多いです。エンディングノートには遺言だけでなく、どう生きていきたいか、どこで最期を迎えたいか、どんな介護サービスを利用したいかなどを記載する欄もあります。これは本人の意思として介護や生活の方針を決めるのに大いに役立ちます。
エンディングノートについてはこちらの記事にまとめていますのでご参照ください。
家族間の介護トラブルを生まないポイントみっつ目、本人の意見を尊重することを解説しました。
家族間の介護トラブルを避けるポイント3つを解説しました。
● 不公平感の少ない役割分担
● 中立な第三者を交えて話をする
● 本人の意見を尊重する
これらを参考に、介護の方針を決めていくことをお勧めします。
重要なのは情報共有
また、役割分担しながら介護を行う際に重要なのが情報共有です。

役割を分けることで、兄弟間で情報の量や内容についてのギャップが生まれます。ケアマネジャーや医師からの話を聞いて専門職の視点からのアドバイスを受けている側と、そうでない側では考え方も変わります。
逆に、認知症がまだらに出現する場合や、身体状況の日内変動が多い場合など、いい状態と悪い状態が交互にある高齢者もいます。この場合、いい状態ばかりを見ている人と、悪い状態ばかりを見ている人では、その人の状態のとらえ方が異なります。
このような情報のギャップを防ぐためには情報共有が必要です。LINEなどのチャットツールなどを使ってグループで情報共有することをお勧めします。介護保険証の情報などをアプリで写真に撮っておいたり、受診の際の医師のアドバイスをメッセージとして残しておいたり、本人の状況がおかしいときには動画に残しておくなど、チャットツールを使って情報共有することでお互いの認識を統一することができます。
こまめな情報共有ができると、お互いの動きや介護への協力なども見えるようになります。情報共有の方法などもあらかじめ決めておくことをお勧めします。
まとめ
介護をめぐる兄弟・姉妹・親族間のトラブルはとても多く、泥沼化してしまう場合もあります。
それぞれの置かれている状況を踏まえ、相手の立場を尊重しながら話し合いを行いましょう。介護は非常に負担の大きいことであり、誰かひとりに負担を負わせないよう、それぞれが自分にできることを考えることで解決できます。
ただ、一番大事なことは、介護が必要になる前から話をする機会を持つことです。介護が必要になったら、認知症になったら、自分でトイレに行くこともできなくなったら。
どんな場所でどう生きていきたいのか、あらかじめ本人の思いを家族間で共有しておくことが円満介護の最大の秘訣です。
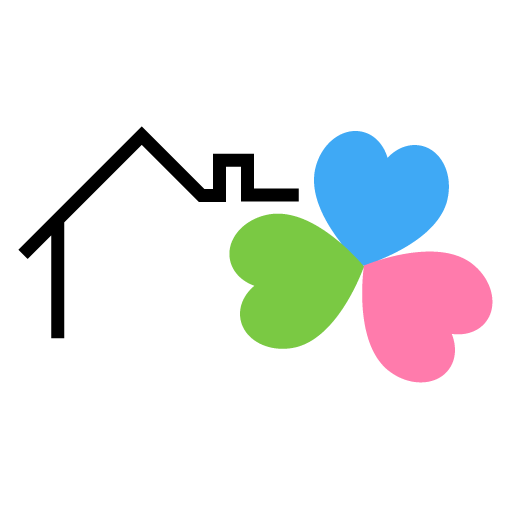
この記事を執筆・編集したのは
いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)