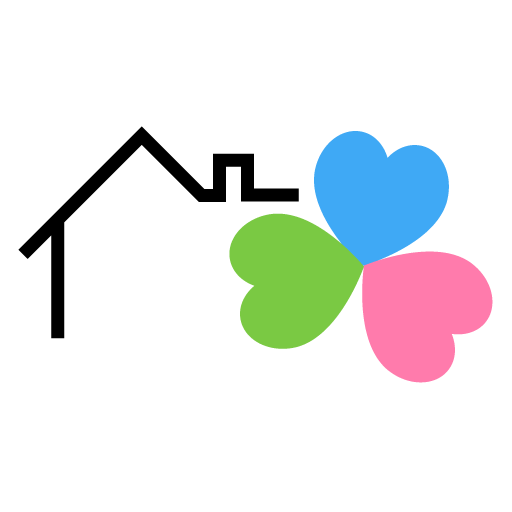
いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
自宅で介護をするために、とても大事なのが介護をする環境です。
介護者側から見て介護を少しでも楽にするために重要であるとともに、介護される側も快適で過ごすためにはその生活環境を無視することはできません。
こんな相談をいただいています。
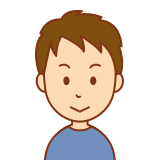
ずっと元気だった母が転倒して大腿骨を骨折。今はリハビリ病院で入院中です。今後は退院して自宅で生活することになりました。
でも、私も妻も仕事をしているので、日中は母一人になってしまいます。今まで母は2階の自分の部屋を寝室にしていたのですが、病院からも1階を寝室にして階段の移動をしないようにと言われています。1階にある和室を母の寝室にできるのか、また、寝室には何を準備したらいいのか。介護もはじめてのことなので、わからないので教えてください。

相談ありがとうございます。初めての介護で心配ですね。
階段移動が難しいので1階で生活することになり、どんな生活環境にすればいいのかを悩んでいるんですね。
わかりました。自宅での生活環境についてヒントになるように、介護に適した間取り・生活環境についての情報をお伝えします。
【この記事を読んでほしい人】
- 病院からの退院や呼び寄せ等で、新たな環境を作る必要があり、困っているご家族様
- 介護が必要な状況になることを見越してあらかじめ新築住宅の間取りを検討している方
- 介護の間取りについて相談を受けて提案をする予定のケアマネジャーさん
【この記事でお伝えしていること】
- 介護に適した部屋の選び方、5つのポイント
- 部屋を介護をしやすくするための5つのポイント
介護に適した部屋はどんな部屋か
介護に適した部屋はどんな部屋?いくつか介護をするための部屋の選択肢がある場合、どの部屋を介護のための部屋にするべきか。
迷ったときには、以下の5つのポイントをもとに部屋を選ぶといいでしょう。
1.トイレへの距離が短い

一番気を付けたいのはトイレまでの距離です。屋内での移動で、最も頻度の多いのはトイレへの移動です。特に、トイレは夜間も移動することが多いです。トイレまでの距離が長いと、介助が必要になる場面も増えます。夜中にトイレを介助するために駆け付けなければいけないとなると、介助する側の負担も大きくなります。また、介助される側も申し訳なく感じてしまうでしょう。
寝室(ベッド)とトイレまでの距離を短くし、安全な動線にすることでトイレ・排せつに関する動作をより自立したものにすることできます。まず最初に、トイレに近い部屋であることを条件に考えるといいでしょう。
2.動線に段差が少ない
段差についても注意しましょう。部屋の入口に段差があると、それを乗り越える際に転倒事故が起こるリスクがあります。部屋の中に段差があるかどうかだけでなく、トイレまでの動線に危険な段差はないか、リビングに移動するまでに大きな段差はないかなど、生活動線の移動のしやすさを確認しましょう。
慣れている2階で生活したい、寝室は日当たりのいい2階がいい、という気持ちもとてもわかります。その思いも当然尊重すべきで、できることならそれが理想です。ただ、状態的にそれが難しい場合は、やはり階段の移動は転倒・転落という重大事故につながりかねない大きなリスクです。安全に暮らすためには段差の少ない場所を検討することをお勧めします。
3.換気・空気の入れ替えができる
窓があって換気ができることも大事な要素です。介護をしているとどうしても部屋には臭いがこもりやすくなります。気密性の高いマンションなども多く、空気の入れ替えができない部屋は介護に適していません。においをこもらせないよう、換気のしやすい部屋にすることをお勧めします。
換気ができない部屋は臭いだけでなく、様々な問題が起こります。湿気のこもりやすいことや、ウイルスやハウスダストなどが充満しやすいこと。これらも介護をしていくうえでは大きな課題となります。
4.日当たり・照明の明るさ
日当たりはとても重要です。日の光を感じることで生活リズムが整いやすくなり、季節を感じることもできます。外の景色を見えることができれば様々な刺激が入ってきます。
照明が暗いと、特に認知症の方は混乱しやすくなります。薄暗い環境だと、幻視・幻覚が見えることも多くなります。できるだけ影を作らず、明るい部屋であることが望ましいです。
5.家族とのコミュニケーションがとりやすい

最後に家族とのコミュニケーションの取りやすさです。本人の過ごす寝室と、家族の過ごすリビングが遠く離れていると、声が聞こえず、生活感が感じられません。何か用があるときには呼び出しのベル(インターフォン)・電話などで伝えるとしても、やはり距離が遠いと互いに足も遠のきます。
あえて遠くにする理由もあるかもしれませんが、基本的にはリビングとの近接性のある部屋にすることでコミュニケーションの機会を増やすことをお勧めします。
以上、介護に適した部屋を選ぶための5つのポイントを紹介しました。
費用をかけずに、介護をしやすい部屋にする
では、今の部屋をより介護しやすくするためのポイントを紹介します。もちろん、家全体をリフォームして、完全バリアフリーの住宅にすれば介護をしやすい部屋を作ることはできます。ただ、費用や時間がかかるようでは難しいため、手間をかけずに簡単にできるポイントに絞って、こちらも5つ紹介します。
1.ベッドの配置

まずはベッドの配置をどうするか考えましょう。
ベッドは壁ぴったりギリギリに設置するのではなく、人が一人入れるくらいのスペースを空けておくことをお勧めします。二人で介助をする場合に、ベッドの両側から介助できるようになります。
出入口までの移動距離も大事なので、部屋の出入口までの距離があまり長くならないようにしましょう。
脳梗塞の後遺症などで身体に麻痺がある場合などは、ベッドの向きにも注意しましょう。例えば、右半身に麻痺がある場合、体を起こすときには動く左手を使います。左肘で体を支えながら体を起こすことで、ベッドに端座位(ベッドに腰かけた状態で足を床に下す座位姿勢)をとることができます。なので、半身麻痺がある場合は、麻痺のない側を通路側、麻痺がある方を奥(壁)側にすることで、麻痺のない側を使って起き上がって、その手でベッドのサイドレールを掴み、立ち上がって歩くことができます。
また、ベッドの位置とコンセントの位置にも注意しましょう。ベッドは電動ですので、電源とコードでつなげる必要があります。コードが動線上にあると足を引っかけてしまう恐れがあります。電源コードが邪魔になりそうなときは、コードを延長するなどして、動線に影響がないようなルートに変更しましょう。
ベッドの時間が長くなりそうであれば、ベッドサイドテーブルなども用意しておくことをお勧めします。
2.手すりの取付け
ポイントポイントに手すりを取り付けることも大事です。その方の歩行の状況などによっても手すりの設置位置や形状は異なりますが、姿勢を安定し、転倒を予防するためには手すりは大きな意味を持ちます。方向転換や段差の昇降、ドアの開閉などの動作が発生する場所に手すりを取り付けると、より安全な移動動作ができるようになります。手すりの取付けであれば、介護保険での住宅改修の対象になります。介護保険を使えると1割から3割の自己負担で工事ができますので、費用負担も少なく済みます。
手すりの取付けに関して詳しくはこちらの記事をご参照ください。
もちろん手すりだけでなく、杖や歩行器などの福祉用具を使うことも含め、移動の安全性の確保を目指しましょう。
3.段差の解消と移動の円滑化
手すりと同じように、介護保険の住宅改修が可能な項目もあります。
段差があれば段差解消の工事ができます。歩行器や車いすで移動するのに段差が障害になる場合は、スロープを取り付けることで安全に移動できるようになります。
また、車いすが移動しにくい部屋の場合は床を変更することもできます。畳の部屋で車いすが動きにくい場合は、介護保険を使ってフローリングに変更することも可能です。もちろんですが、床にはあまりものを置かずに、移動できるスペースを確保しておきましょう。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
4.照明
照明も重要なポイントです。一定程度の明るさを必ず確保できるようにしましょう。
照明の影ができないように、間接照明・足元照明などを使い、特に動線の明るさを保ちましょう。
自分で照明のオンオフをコントロールしやすいように、照明リモコンの置き場所も準備しましょう。また、リモコン類はまとめて置き、ベッドから落ちないようにカゴに入れるか、サイドテーブルに置くなど工夫しましょう。
5.呼び出し用のボタン
緊急時なども含め、家族に連絡するためのコールボタンなどを用意しましょう。室内用の呼び出しベルの種類にもいろいろあります。ボタンで通知ができるだけでなく、通話ができるタイプのもの、子機を増設できるタイプのものもあります。
最近では、ブルートゥース機能がついていて、ペアリングしているスマートフォン等の携帯端末に通知をすることができる介護用ベッドもあります。状況に合わせて適切な商品を選ぶようにしましょう。
以上、介護をしやすくするためのポイントを5つ紹介しました。
介護をしやすくするというだけでなく、本人にとっての快適さを考えると、他にも様々な要素が考えられます。
- テレビの置く場所と向き
- パソコンを使う人はパソコンの置き場所
- 部屋の装飾品・雰囲気
- 大切な写真などが見える場所にあるか
自分の居場所だと感じられるものが身近にあるだけでも気持ちが落ち着きますよね。
まとめ
介護のしやすい間取りについて解説しました。
介護が必要になる状況になると、外出や移動も制限が多くなり、自室で過ごすことも増えます。自室での暮らしも快適に過ごせるようにしたいですよね。
ぜひ参考にしていただければと思います。
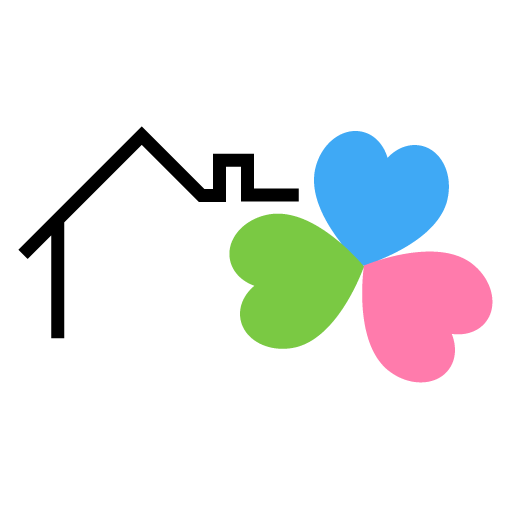
この記事を執筆・編集したのは
いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

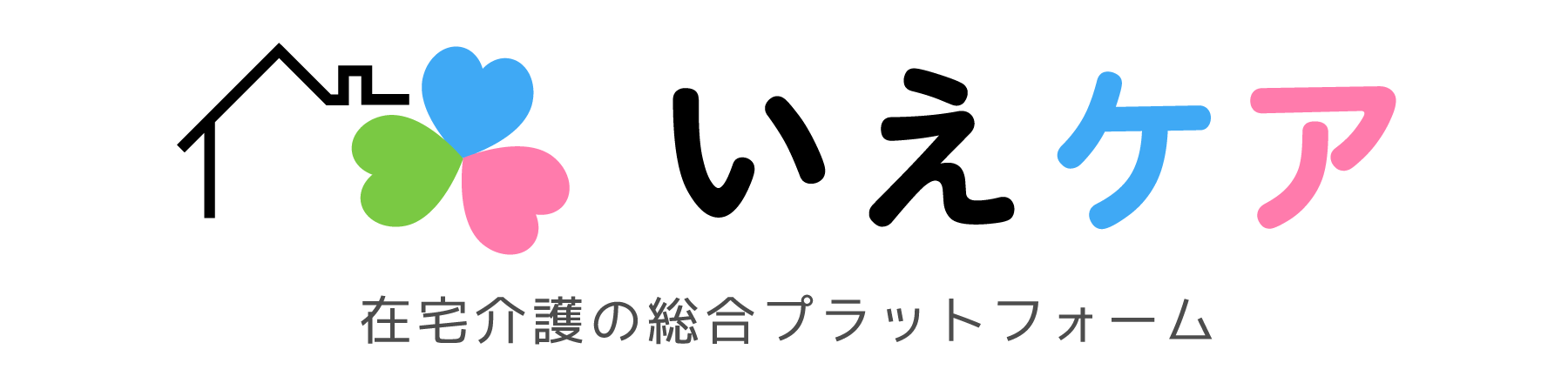







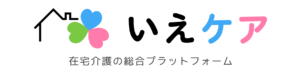


コメント