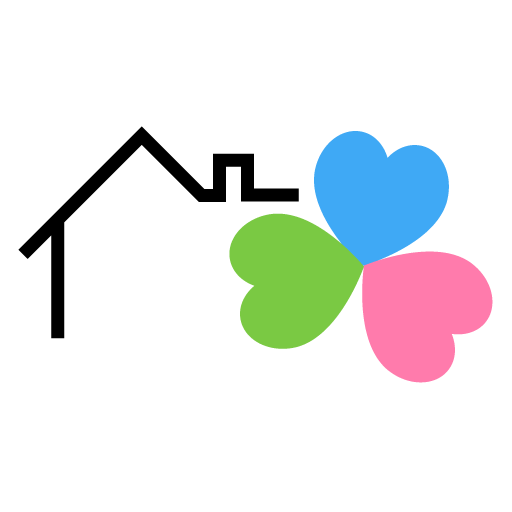
いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

「毎日が時間との勝負。電話が鳴れば休憩もそこそこに、次の訪問先へ向かう。」
ケアマネジャー(介護支援専門員)の日常は、こうした慌ただしい光景で彩られています。利用者や家族の思いに寄り添いながら、医療・介護・行政をつなぐ役割を担う一方で、自分の健康や生活リズムは二の次になりがちです。
そんなケアマネの「悩み」を、数字として可視化したのが厚生労働省所管の「介護労働実態調査」です。この調査は全国の介護職種を対象に、労働条件や職場環境、日々の不安や不満を幅広く聴き取ったもの。令和6年版では、ケアマネならではの負担や不安が改めて浮き彫りになりました。
本記事では、令和6年調査の結果からケアマネの悩みトップランキングを紹介し、特に上位5項目について背景や原因を解説していきます。数字の裏にある“現場の声”を紐解きます。
【この記事を読んでほしい人】
- 仕事上の悩みを持っているケアマネやケアマネ事業所運営法人
- ケアマネの困りごとを解決しながら良好な関係を作っていきたい介護サービス事業所
【この記事に書いてあること】
- 介護労働実態調査から見るケアマネの悩みランキング
- 過去のランキングから急激に伸びている項目について
「介護労働実態調査」とは? 介護職・ケアマネの悩みを可視化する全国調査
介護の現場は、制度やニーズの変化に合わせて常に動き続けています。その中で働くケアマネジャー(介護支援専門員)の声を、数字として浮かび上がらせるのが「介護労働実態調査」です。
この調査は、公益財団法人介護労働安定センターが毎年全国規模で実施しているもので、介護職員の労働条件や職場環境、就業意識を明らかにすることを目的としています。調査結果は、人材確保・育成、職場改善、介護サービスの質向上など、現場の課題解決に活かされます。
令和6年度調査は、全国の介護保険サービス事業所とそこで働く職員を対象に行われ、有効回答は事業所調査で9,044件、労働者調査で21,325人分にのぼりました。本記事で注目するのは、この労働者調査の「悩み・不安・不満」項目。複数回答形式で、現場で働く人が日々感じている問題を率直に回答してもらった結果です。
なかでもケアマネは、訪問や会議、書類作成といった多忙な日々の中で、独特の悩みや負担を抱えています。こうした声は日常業務では表に出にくく、同じ立場の仲間同士でも共有されないことがあります。
そこで今回は、令和6年度の調査データからケアマネがどんな悩みを抱えているのかをランキング形式で紹介し、さらに上位項目についてはその背景や原因を掘り下げていきます。過去の調査との比較から見えてくる変化についても解説します。
ケアマネの悩みトップ10(令和6年調査)
令和6年度「介護労働実態調査」の労働者調査から、ケアマネジャー(介護支援専門員)が回答した「悩み・不安・不満」の上位10項目を抽出しました。割合は、回答者のうちその項目を選んだ人の比率(複数回答)です。
| 順位 | 悩み項目 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1 | 仕事内容のわりに賃金が低い | 36.5 |
| 2 | 精神的にきつい | 31.5 |
| 3 | 業務に対する社会的評価が低い | 24.6 |
| 4 | 人手が足りない | 21.8 |
| 5 | 休憩が取りにくい | 13.2 |
| 6 | 健康面(感染症・怪我等)の不安 | 13.1 |
| 7 | 有給休暇が取りにくい | 10.6 |
| 8 | 夜間・深夜帯に何か起きる不安 | 7.9 |
| 9 | 身体的負担が大きい | 7.7 |
| 10 | その他 | 6.8 |
上位には「賃金」「精神的負担」「社会的評価」といった待遇や評価に関する悩みが並びます。続いて「人手不足」「休憩が取りにくい」など、日々の業務環境に直結する課題が目立ちます。
なお、「労働条件・仕事の負担について特に悩み、不安、不満等は感じていない」という回答がなんと18.8%もありました。これは、上司や経営者の目の前で書かされたか、面倒だったからそのようにつけたか、いろいろな事情がある可能性もありますが、仕事に対する悩みを持っていない方も一定数いることがわかります。
次のセクションでは、このうち特に上位5項目を取り上げ、その背景や原因を深掘りしていきます。
ケアマネの悩みトップ5の背景と原因
1位 仕事内容のわりに賃金が低い(36.5%)

最も大きな悩みとなっていたのが、仕事内容のわりに賃金が低いというものでした。
ケアマネの業務は、ケアプラン作成、アセスメント、関係機関連携、利用者や家族との面談、記録作成など多岐にわたります。これらは単なる事務作業ではなく、介護保険制度や医療知識、心理的配慮を伴う高度な専門性が必要です。資格取得のために多くの経験と、試験の合格、資格維持のための研修と、業界内でも取得・維持ハードルの非常に高い資格です。
しかし、介護報酬制度の仕組みではケアマネの報酬単価が限られ、処遇改善加算の直接対象にならない場合も多いのが現状です。昇給幅も小さく、経験やスキルが十分に評価されにくいため、「責任の重さに対して報われない」という実感が広がっています。さらに、介護職員の処遇改善が進んだことで、ケアマネと介護福祉士等の賃金の逆転現象が起きていることもケアマネの不安につながっています。
現場の声:「毎月の給料明細を見るたび、やりがいだけでは続けられないと感じる」
2位 精神的にきつい(31.5%)
ケアマネは常に「板挟みの職種」です。利用者や家族の要望、介護・医療現場の事情、制度上の制約、法人の意向、それぞれ異なる立場を調整しなければなりません。
さらに、利用者の生活や命に直結する判断を迫られることもあり、その責任感は相当なものです。緊急対応や苦情処理、時には感情的なやり取りも避けられず、気持ちが休まる時間を持ちにくいのが実情です。
現場の声:「利用者と事業所、両方の希望を叶えたいけれど、制度の壁が立ちはだかる」
3位 業務に対する社会的評価が低い(24.6%)
ケアマネの仕事は外から見えにくく、利用者や家族、地域社会からは「何をしている人なのか」が理解されにくいことがあります。利用者の生活が安全に維持されるために様々なサポートを行っているものの、その多くは目に届きにくい現実があります。
介護報酬自体もほぼ上がらず、居宅介護支援だけで事業所を黒字化するためには、事業所を大規模化・特定事業所化するなどの工夫が必要になります。ただ、そのためにはケアマネに様々な負担を強いることにつながり、結果としてモチベーション低下につながります。
現場の声:「調整や電話対応、書類作成であっという間に一日が終わる、誰にも見られない努力だと感じる」
4位 人手が足りない(21.8%)
少子高齢化の進行でケアマネの需要は高まる一方、有資格者の確保は難しくなっています。特に都市部では、担当件数が法定上限ギリギリか、それを超えるケースもあります。業務量が多すぎると、一件ごとの対応品質に影響が出るだけでなく、残業などの労働負荷がますます大きくなっていきます。
過疎地域ではケアマネがいないためにサービスが利用できないケアマネ難民が発生する状況。さらに、管理者要件や特定事業所要件に、主任介護支援専門員を確保しなければいけないことなど、人材確保は非常に大きな問題となっています。
現場の声:「1人で抱える件数が多すぎて、じっくり向き合いたくても時間が足りない」
5位 休憩が取りにくい(13.2%)
訪問・会議・電話対応など予定が詰まり、昼休みが数分で終わることも珍しくありません。人員不足が背景にあり、休憩中も緊急連絡が入ればすぐ対応に回らなければならない状況です。昼の方が電話につながりやすいからと、昼休みを狙って事業所に連絡をする事業所も多いです。
こうした「休憩できない休憩時間」が積み重なると、疲労やストレスの蓄積、健康面への悪影響が避けられません。
現場の声:「お昼休憩を取った記憶がない日が続いているけれど、だんだん感覚が麻痺してきた」
この5項目はいずれも、制度的制約や構造的課題が背景にあります。次のセクションでは、この中でも特に近年大きく変化しているひとつの項目に焦点を当て、令和元年との比較とその背景を詳しく見ていきます。
健康面の不安はなぜ急増したのか(令和元年3.9% → 令和6年13.1%)

令和元年の調査結果と比較してみると、改善されている項目も多くあります。
「有給休暇が取りにくい」は17.8%から10.6%に、「休憩が取りにくい」も16.1%から13.2%に減少。「労働時間が長い」は7.4%から5.2%に減少。労働環境に関する悩みや不満は事業者側の取り組みにより改善されている傾向が明らかです。
そして、ここで注目してほしい項目がひとつあります。それは「健康面の不安」です。
介護労働実態調査において、「健康面(感染症・怪我等)の不安」を選んだケアマネは、令和元年にはわずか3.9%でした。ところが令和6年調査では13.1%と、わずか数年で3倍以上に増加しています。
この変化の背景には、大きく2つの要因があると推測されます。
1. 新型コロナウイルス感染症による長期的な影響
2020年以降、利用者宅や施設での感染リスクと常に向き合ってきました。
- 高齢者や基礎疾患を持つ利用者への感染を防ぐため、感染対策は常に最優先事項に
- 面談時のマスク着用、換気などの手間と時間的負担
- 利用者や家族の感染による急な対応
いまだに介護現場では新型コロナウイルスの感染リスクは大きく、利用者の中では感染して重篤な症状を発症する方も少なくありません。こうした環境下で「自分も感染してしまうのでは」という恐れと、「利用者にうつしてしまうかもしれない」という二重の不安が続き、健康不安の意識を押し上げました。
2. ケアマネ自身の高齢化
介護支援専門員の平均年齢は年々上昇しており、50代・60代が多数を占めます。今回の調査で、ケアマネの平均年齢は54.3歳に達したことが報告されています。見方を変えれば、経験豊富な人材が多いことを意味しますが、同時に持病や体力の衰えと向き合いながら働く人も増えているということでもあります。
- 長時間のデスクワークや外回りによる腰痛・関節痛
- 加齢に伴う持病管理と仕事の両立
- 感染症への抵抗力低下
このように「自分自身の健康リスクをより身近に感じる年齢層」が増えたことも、数字の上昇に直結しています。
二つの要因が重なる現場のリアル
感染症の脅威と年齢的リスクの増大は、相乗的に健康不安を高めます。
健康面の課題や不安を抱えながらも、人手不足のために辞めるにも辞められないという状況にある超ベテランケアマネも少なくないのです。若い世代が増えない中、ベテランケアマネにいつまで依存し続けなければいけないのか。大きな構造的な課題を抱えています。
まとめ 〜数字の裏にあるケアマネの声を知る意味〜
令和6年「介護労働実態調査」の結果から、ケアマネジャーが抱える悩みの上位には、賃金、精神的負担、社会的評価、人手不足、休憩の取りにくさといった、制度や職場環境に起因する課題が並びました。
さらに、健康面の不安は令和元年の3.9%から13.1%へと急増。ケアマネ自身の高齢化という背景が、その意識を押し上げています。
数字を知り、現実を理解することは、働く人を支えるための第一歩です。今回の調査結果が、ケアマネの待遇改善や課題解決につながる後押しになることを期待します。
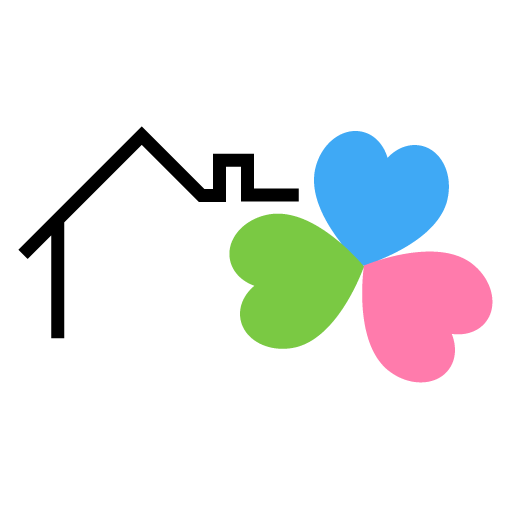
この記事を執筆・編集したのは
いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

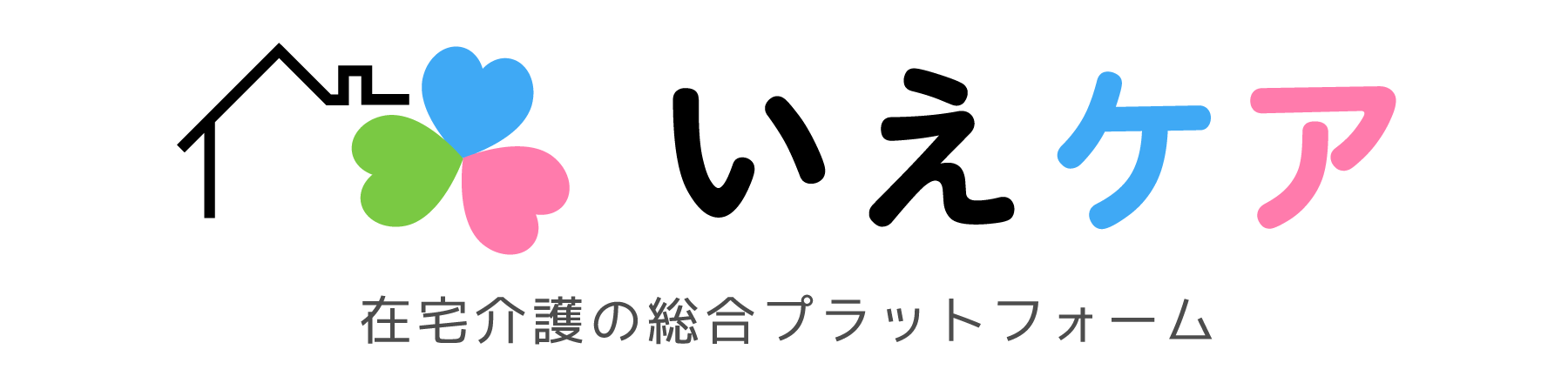
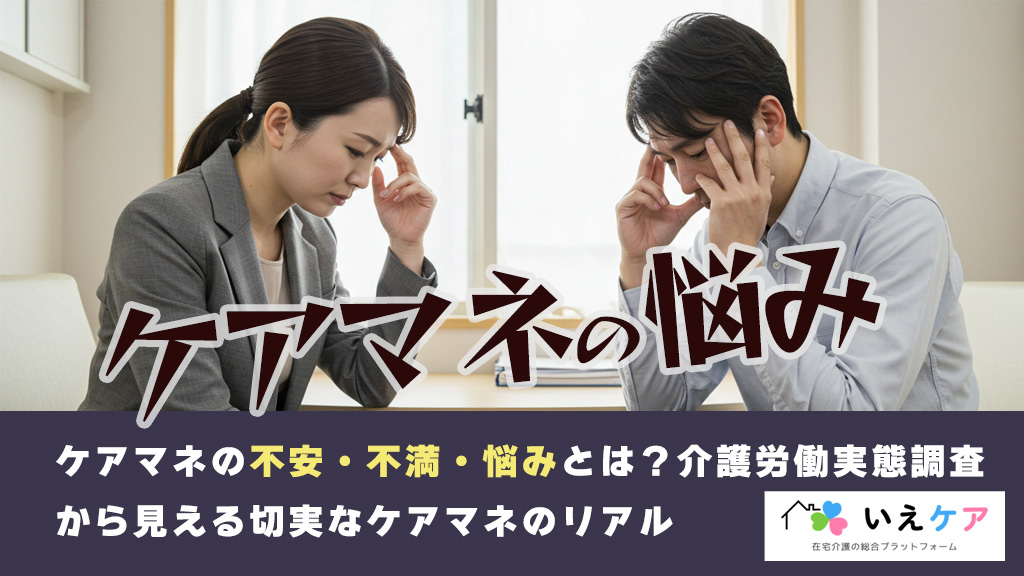


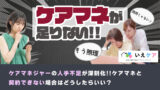


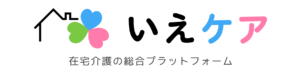


コメント