
この記事を監修したのは
介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役
河北 美紀
デイサービスは、通常1回当たり1,000~2,000円程度の料金がかかります。しかし実際に複数の要素が複雑に絡み合って決まっているため、どのくらいかかるのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。今回は、デイサービスの料金について詳しくご紹介していきます。この記事を読めば、デイサービス利用料の仕組みや自己負担を抑える方法が分かります。ぜひ最後までご覧ください。
★こんな人に読んでほしい!
- デイサービスの料金を知りたい方
- デイサービスをすでに受けており、料金の内訳について知りたい家族の方
- 費用を抑える方法や利用できる助成制度を知りたい方
★この記事で解説していること
- デイサービスの料金は、要介護度・利用時間・地域・施設の規模や種類によって異なる
- デイサービスの費用を抑えるには、利用時間・事業所の規模・加算内容・実費負担分について見直す
- サービス利用料の支払いが大変な時は、各種助成制度を活用する
- デイサービスを選ぶときは、重要視するポイントをケアマネに伝えて相談する
1. デイサービスの料金
1-1. デイサービスの料金は要介護と要支援で異なる

デイサービスの料金は、介護サービス料と介護保険適用外費用に分けられます。なかでも介護サービス料は、要介護認定が「要介護1~5」「要支援1・2」のどちらなのかで大きく異なります。要介護のデイサービスは厚生労働省が定めた全国一律の基準で実施されていますが、要支援のデイサービスは各市区町村が独自に「地域支援事業」として実施されているからです*1*2。
まずは、要介護の場合と要支援の場合それぞれの介護サービス料についてご紹介します。
1-1-1. 要介護の場合の料金は1回ごとの課金制
要介護の場合の料金は、以下の要素によって変動します。
- 施設の規模(前年度延べ利用者の月平均人数)
- サービス提供時間(1時間単位)
- 要介護度
- 各種加算の算定状況(事業所ごとに対応している加算が異なる)
施設の規模は「通常規模」「大規模1」「大規模2」があり、利用者の人数が多ければ大きいほど利用料の基本単価は下がります。また、サービス提供時間が長ければ長いほど・介護度が高ければ高いほど基本単価は上がる仕組みです。
厚生労働省がデイサービスの利用実態をまとめた「社会保障審議会 介護給付費分科会 第180回 資料1」によると、最も利用頻度が多いのは「通常規模」の事業所*1で、利用している時間は「7時間以上8時間未満」*1でした。この条件でデイサービスを利用した場合の料金は、以下の通りです*3。
| 要介護度 | 基本サービス料 |
| 要介護1 | 658円/回 |
| 要介護2 | 777円/回 |
| 要介護3 | 900円/回 |
| 要介護4 | 1,023円/回 |
| 要介護5 | 1,148円/回 |
※「通常規模事業所」を「7時間以上8時間未満」で利用した場合(2024年4月改定版)
要介護の場合は1回利用するごとに基本サービス料が加算されていく仕組みです。基本料金は事業所の状況や実際のサービス利用時間によって細かく変動します。詳しくは担当のケアマネジャーから確認してもらうようにしましょう。
デイサービスの利用料金の基準となる介護報酬は3年に1回見直されています。2024年の報酬改定で、デイサービスの料金もわずかですが、上昇しています。これは食材費や光熱費、送迎に必要な燃料費などのコストが高騰していることも大きな要因となっています。また、介護職員の賃上げの原資となる処遇改善加算も上乗せされています。金額の変更について、詳しくはデイサービスの相談員に確認することをお勧めします。
1-1-2. 要支援の場合の料金は回数制あるいは月額制(自治体による)
要支援の場合は、以下の要素によって料金が変動します。
- 要介護度
- ひと月当たりの利用回数(一部の自治体)
- 各種加算の算定状況(事業所ごとに対応している加算が異なる)
要支援の方が利用するデイサービスは、以前は「介護予防通所介護」として介護保険サービスのひとつとして厚生労働省が料金体系やルールを決めていました。しかし、平成29年度からは「地域支援事業」の中の「介護予防・日常生活支援総合事業」として市区町村が独自に行うサービスに完全移行しています*2。要支援の場合は市区町村ごとに料金設定が異なるので、実際に料金を確認する場合はお住いの自治体のWebサイトなどで確認しましょう。
ここでは、一例として完全月額制である北海道旭川市と、回数制の山形県鶴岡市を比較しながらご紹介します。
| 要介護度 | 北海道旭川市*4 | 山形県鶴岡市*5 |
| 要支援1(週1回利用を想定) | 1,672円/月 | 1,672円/月 |
| 55円/日※契約期間が1月に満たない場合 | 384円/回 ※月4回まで | |
| 要支援2(週2回利用を想定) | 3,428円/月 | 3,428円/月 |
| 113円/日※契約期間が1月に満たない場合 | 395円/回※月5~8回まで | |
| 請求ルール上の特徴 | 月途中の契約開始や終了の場合は日割り請求となる 完全に月額制の料金である | 要支援1の方は月4回まで、要支援2の方は月8回までは回数ごとに課金される 要支援1の方は月5回以上、要支援の方は月9回以上利用した場合は月額料金になる |
※1単位=10円、自己負担割合1割の場合
このように、基本サービス料は「要支援1の人は週1回程度の利用で月額1,672円」「要支援2の人は週2回程度の利用で月額3,428円」で大枠は同じです。しかし、1月ごとの利用回数によって単価が変動する自治体や、月途中の開始・終了が日割り計算となる自治体など、細かい部分で違いがあります。詳しくはお住いの自治体のWebサイトを確認するか、最寄りの地域包括支援センターに問い合わせるとよいでしょう。
1-2. 基本サービス料以外に料金が変動する要素3つ
デイサービスの基本サービス料以外に料金が変動する要素は、以下の3つがあります。
- 各種加算
- デイサービスの種類
- 事業所が所在する地域
上記3つの要素についてご紹介します。
1-2-1. 各種加算

介護保険サービスの料金は基本サービス料と加算に分けられており、デイサービスも例外ではありません。加算には、基本サービスに加えて提供するオプションサービスに該当するものや、より手厚く所定の人員を配置した場合に自動的に算定されるものがあります。また、要介護の方向けのデイサービスと要支援の方向けのデイサービスによっても体系が異なります。
要介護1~5の方が利用するデイサービスにおける主な加算は以下の通りです*3*6*7。
| 加算名 | 概要 | 料金 |
| 生活機能向上連携加算 | 生活機能向上を図るために外部のリハビリ専門職と連携した場合に算定 | 100~200円/月 |
| 個別機能訓練加算 | 利用者ごとに作成した計画に基づき個別に機能訓練を実施した場合に算定 | 20~76円/回 |
| 中重度ケア体制加算 | 中重度の利用者に対応できるよう、所定の体制を整備した場合に算定 | 45円/回 |
| 栄養改善加算 | 管理栄養士が多職種連携の下で栄養改善に関する計画を作成・実施した場合に算定 | 200円/月2回まで |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 管理栄養士以外の介護職員などが栄養状態を確認し担当ケアマネジャーと情報共有した場合に算定 | 5~20円/6ヶ月 |
| 口腔機能向上加算 | 言語聴覚士などが作成した口腔機能管理指導計画に従って口腔機能向上に関するサービスを提供した場合に算定 | 150~160円/月2回まで |
| ADL維持等加算 | 利用者の日常生活動作(ADL)の維持・改善状況が一定の基準を超えている場合に算定 | 30~60円/月 |
| 入浴介助加算 | 入浴介助を実施した場合に算定 | 40~55円/回 |
| 認知症加算 | 認知症に関する研修を修了した職員を一定以上配置した場合に算定 | 60円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 利用者ごとの心身状況や服薬状況などについて厚生労働省のデータベース(通称:LIFE)へ提出し、収集した情報を適切に活用している場合に算定 | 40円/月 |
| 介護職員処遇改善加算 | 勤務する介護職員などの待遇を改善するために算定される加算 | ×3.3~9.2% |
要支援の方向けのデイサービスにおける主な加算は以下の通りです。なお、基本サービス料は自治体ごとに詳細が異なりますが、加算部分に関するルールは基本的に全国共通です*4*5*8。
| 加算名 | 概要 | 料金 |
| 生活向上グループ活動加算 | 共通の課題を持つ複数の利用者グループに日常生活上の支援のための活動を行った場合に算定 | 100円/月 |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態およびそのおそれがある利用者に対して改善を図ることを目的として個別に栄養管理を行った場合に算定 | 200円/月 |
| 口腔機能向上加算 | 言語聴覚士などが作成した口腔機能管理指導計画に従って口腔機能向上に関するサービスを提供した場合に算定 | 150~160円/月 |
| 一体的サービス提供加算 | 栄養改善加算、口腔機能向上加算に相当するサービスを併せて行った場合に算定(新設) | 480円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 利用者ごとの心身状況や服薬状況などについて厚生労働省のデータベース(通称:LIFE)へ提出し、収集した情報を適切に活用している場合に算定 | 40円/月 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 勤務する介護職員などの待遇を改善するために算定される加算 | ×3.3~9.2% |
各種加算は事業所ごとに算定する内容が異なり、中には大きく利用料に影響する加算もあります。基本サービス料ばかりに注目していると思いがけず請求金額が高くなってしまう可能性があるので、利用開始前に実際にケアマネジャーから試算してもらうようにしましょう。
2024年の報酬改定に伴う、運動器機能向上加算・選択的サービス複数実施加算・事業所評価加算が廃止となりました。口腔機能向上と栄養改善の要件を満たすのであれば一体的サービス提供加算が追加となりました(2024年4月1日より)。
1-2-2. デイサービスの種類
一口にデイサービスと言っても、デイサービスには全4種類があります。種類によっても料金や目的が異なるので、利用者の状況に合った種類のデイサービスを選びましょう。
| デイサービスの種類*9 | 特徴 |
| 通所介護(デイサービス) | 通常のデイサービス。1日の定員が20人程度の「通常規模」、30人程度の「大規模1」、それ以上の「大規模2」がある*10。機能訓練特化型デイの多くは介護保険制度上は通常のデイサービスである。要支援の方の場合は料金体系が異なり、要支援1は週1回程度、要支援2は週2回程度と制約がある*11。 |
| 地域密着型通所介護(小規模デイ) | 1日の利用定員が18名の小規模なデイサービス。小規模なのでゆったりとした雰囲気の事業所が多い。利用できる人は以下のように制限されている。要介護1~5の方所在地と同じ自治体に住民票がある方 |
| 療養通所介護 | 医療機関と連携をとれる体制が整備されているため、医療の必要性が高い方や重度の介護が必要な方でも安心して利用できるデイサービス。以下の条件に当てはまる人が利用できる。利用できる人は以下のように制限されている。要介護1~5の方所在地と同じ自治体に住民票がある方 |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方でも安心して利用できる、認知症専門のデイサービス。通常のデイサービスと異なり、要支援の方でも1回単位の料金体系になっている。利用できる人は以下のように制限されている。所在地と同じ自治体に住民票がある方認知症の診断を受けている方 |
デイサービスはさまざまな種類がありますが、利用者の心身状態によって適したデイサービスは変わってきます。何を選んだらいいか分からないと悩んでいる場合は、担当のケアマネジャーとよく相談して決めることをおすすめします。
1-2-3. 事業所が所在する地域

デイサービスを問わず、介護保険のサービス料は事業所が所在している地域によって異なる場合があります。「地域区分」といい、東京23区や政令指定都市のような大規模な都市は補正が入る仕組みがあるからです。
地域区分には「1級地~7級地」「その他」の8段階あり、等級に応じて以下のように介護サービス料が上乗せされます*12。
| 地域区分 | 上乗せ率 |
| 1級地 | 20% |
| 2級地 | 16% |
| 3級地 | 15% |
| 4級地 | 12% |
| 5級地 | 10% |
| 6級地 | 6% |
| 7級地 | 3% |
| その他 | 0% |
詳細は、お住いの市町村や担当のケアマネジャーに問い合わせると確認できます。料金を試算する際に必ずチェックしておくようにしましょう。
1-3. 施設によって介護保険外の費用がかかる
デイサービスを利用するときに必要となるものの中には、介護保険の適応外となって別途自己負担が必要になります。ケアマネジャーが毎月作成する予定表には計上されていない場合もあるので、ご自身で毎月どのくらいの料金が別途必要になるか把握しておくことが重要です。
介護保険対象外となっている費用には、以下のようなものがあります。
- キャンセル料
- 昼食代
- おやつ代
- オムツ代
- 娯楽費
- レクリエーションに必要な物品の実費 など
介護保険外の費用は事業所が独自に設定しています。費用の内訳やキャンセル料が発生する条件は契約時に説明される「重要事項説明書」に記載されています。安易に読み飛ばさず、必ず確認しましょう。
2. 費用をなるべく抑える方法と利用できる補助
2-1. デイサービスの費用を抑えるには?
デイサービスの費用が心配な場合は、以下の方法で料金を抑えられる可能性があります。
- 利用時間を短くする(要介護の場合)
- 規模が大きいデイサービスを選ぶ
- 加算の有無を事前に確認し、不要なものは断る
- 送迎や食事を減らす
利用料金をなるべく抑える方法についてご紹介します。
2-1-1. 利用時間を短くする

要介護のデイサービスの場合、料金は1時間単位で設定されています*3。中には半日単位で利用者を入れ替える半日型のデイサービスもあります。時間数が短くなればその分、一回の利用あたりの報酬単価が少なくなり、料金も安くなります。
短時間のサービスであれば食事の提供はなく、自宅で食事を食べるようになります。最低限必要な時間に絞って利用すれば、デイサービス費用ので大きな割合を占める食費を削減することもでき、利用料金を抑えることができます。
ただしデイサービス事業所の多くは送迎対応可能な時間を定めているため、臨機応変な送迎が困難な場合もあります。利用者側で移動手段を確保しなければならなくなる場合があることも覚えておきましょう。
2-1-2. 規模が大きいデイサービスを選ぶ
デイサービスには「通常規模」「大規模1」「大規模2」と3種類の料金体系があります。通常規模よりも大規模1型、大規模1よりも大規模2型の事業所の方が基本サービス料が安くなっています*3。規模が大きければ大きいほど賑やかになってしまいますが、費用を優先する場合は大規模タイプの事業所を利用することがおすすめです。
2-1-3. 加算の有無を事前に確認し、不要なものは断る

デイサービスの料金に影響する加算は、各事業所により異なります。少しでも料金を抑えたいと思うなら、なるべく加算が少ない事業所を選ぶ方法があります。ただし、加算の内容は事業所の職員配置状況やサービス内容などを反映しており、サービスの質にも関係の深い指標です。加算内容が少ない事業所はサービスの質が不安視される部分もあるので、ケアマネジャーとよく相談するようにしましょう。
また、「自宅で入浴できるならデイでは入浴しない」「自分なりに運動しているから個別機能訓練は不要」「定期的に歯科受診しているから口腔機能向上サービスはいらない」など、一部の加算は算定を断ることも可能です。加算はすべて選択しなければいけないわけではないので、担当のケアマネジャーさんとも相談しながら、加算の選択は必要性を踏まえて検討しましょう。
2-1-4. 送迎や食事を減らす

ここからはあくまで参考として、費用が減る方法を紹介しますが、デイサービスの基本となるサービスの一部を削る内容ですので、推奨はしません。
デイサービスの送迎費用は基本料金に含まれています。自分で運転してデイサービスに通ったり家族から送迎してもらったりすると「送迎減算」が適用される*3ので、費用を抑えることができます。
ただし、多くのデイサービスでは送迎もサービスの一部ととらえており、道中に事故などがあるリスクを避けるためにも基本的に送迎は必須としていますので、通所方法についてはご確認ください。
また、中には食事を持参することで昼食代を請求されないようにしている方もいます。中には元々の生活習慣で昼食を摂らない方や、経管栄養で栄養剤を持参する方もいるので、その場合は昼食の提供をお断りすることもできます。ただし食品衛生の面などから食事の持込みができない事業所もあること、またその時間は疎外感を感じる場合もあるので、サービス開始前にケアマネジャーとよく相談しましょう。
2-2. 在宅介護を受けている方が利用できる補助
なるべく介護費用を抑えるため、公的な助成制度を活用する方法があります。補助を受けるためには手続きや所定の条件を満たす必要があります。デイサービスを利用している要介護者が利用できる制度には、以下のようなものがあります。
- 高額介護サービス費
- 高額介護合算医療費制度
- 障害者控除
- 医療費控除
- おむつ券支給制度
- 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度
それぞれの概要をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
2-2-1. 高額介護サービス費
介護サービス利用料の合計月額が限度額を超えた場合に、差額が払い戻される仕組みです*13。一般的な所得の方の限度額は44,400円で、申請先は住民票がある自治体です。負担上限額は所得に応じて異なります。一度申請をすると、以降は自動的に指定した口座に振り込まれます。
2-2-2. 高額介護合算医療費制度
一年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、基準額との差額を払い戻すことで費用負担軽減を図る仕組みです*14。75歳以上で住民税非課税の方の場合は基準額が年間31万円と設定されているため、たとえば年間50万円かかった場合は差額の19万円が払い戻されます。申請先は住民票がある自治体です。
2-2-3. 障害者控除
要介護認定を受けている方が自治体の介護保険担当窓口に申請すると、税制上の障害者控除の対象者として認めてもらうことができる仕組みです。確定申告の際に障害者控除を申請すると所得控除を受けられることによって住民税が安くなる可能性があります。自治体が実施している各種助成制度は住民税非課税であることが条件となっているものが多いので、要件に該当する場合はぜひ行っておきたい手続きです。
対象となる要件は自治体によって異なるので、まずはお住いの役所に問い合わせてみましょう。
2-2-4. 医療費控除
医療費控除を行うと所得税や住民税の節税につながるため、間接的に費用を抑えることができます。デイサービスのみ利用している場合は対象になりませんが、「訪問看護」や「通所リハビリテーション(デイケア)」などの医療系サービスと併用している場合はデイサービスにかかった費用も医療費控除に算定することができるようになります*15。
また、所定の手続きを行えばおむつの購入にかかった費用も医療費控除の対象になります*15。
詳しくはこちらの記事を参考にしていただき、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
2-2-5.おむつ券支給制度
各自治体では、おもに常時失禁状態にある方に対しおむつの購入を支援する制度を設けています。在宅で過ごしている方が対象で、自治体ごとに制度の名称や条件・支給方法の詳細は異なります。
一般的には「おむつ支給」や「おむつ券」などと呼ばれています。申し込みは自治体に直接行う場合と最寄りの地域包括支援センターが申請窓口になっている場合があるので、詳しくは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。
2-2-6. 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度
低所得でとくに生計が困難な方が必要な介護サービスを利用できるようにするために作られた制度です。条件に該当する方が社会福祉法人・市区町村が実施する所定の介護サービスを利用した場合に、利用料負担の一部が軽減されます。対象となるのはおもに年間収入や預貯金額などの合計が一定以下です*16。申請は市区町村に実施します。
3. デイサービスの利用料金、支払い方法は?
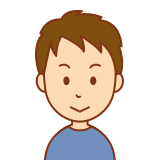
デイサービスの利用料金がどのくらいかは分かったんですけど、料金ってどうやって支払うの?一回ごとに支払うの?いつ支払うの?現金払い?
デイサービスの料金の支払い方法について紹介します。
料金は一か月分をまとめて後払い
利用料金の支払い方法は一か月分をまとめ払いです。
加算も含めた介護保険の自己負担分の料金、食事代などの実費負担分も含めて、一か月の利用分をまとめて支払います。介護保険の限度額を超過した金額などが発生した場合などの保険外料金も合算した金額を支払います。
支払いのタイミングは利用月の翌月
支払いのタイミングは基本的には利用月の翌月となります。なぜかというと、介護保険の点数計算などがあり、ケアマネジャーとの確認・調整が必要になる場合があるからです。デイサービス事業者が国に介護報酬となる点数を報告してから利用者負担分の請求書を発行するパターンが一般的です。
事業者によってタイミングに誤差はあると思いますが、翌月中旬から後半にかけて請求が発行されます。翌月になっても、まだ支払いの請求がなくて、大丈夫かな・・・と心配される方も多いのですが、利用から請求まで一か月近く時間がかかるということを覚えておいてください。
また、利用がもう終了しているのに請求書が来た、と驚く方もいますが、利用した月から遅れて請求書が発行されるためです。
支払い方法は事業所によって異なるが、口座振替が多い
支払い方法は事業所によって異なります。
一般的に最も多いのは銀行口座から引き落とされる口座振替です。口座振替のメリットは現金の用意が必要ないことで、職員が現金などを扱うことがなく、確実性が高いことです。
事業者によっては現金払いのみにしているところもあります。デイサービス利用者のカバンに集金袋と請求書を入れ、金額を集金袋に入れてデイサービスで受け取るという方式をとることが多いです。
他にも、コンビニ払いや銀行振り込みなどの支払い方法が選択できる場合もあります。どのような支払い方法をとっているのかは事業所によって異なりますので、事業所に直接確認することをお勧めします。
4. よいデイサービス選びは、利用目的と重視するポイントの明確化が大切
大事なことを最後にお伝えします。デイサービス選びは料金・費用だけで決めてはいけません。
少しでも安いところを選ぼうとすると、最悪、このような状況に陥ることもあります。
デイサービス選びは金額で決めずに、様々な要素を加味して慎重に行いましょう。
利用者に合ったデイサービスと出合うためには、「デイサービスに何を求めているか」「サービス内容のどの部分を重視しているか」と言う点に絞って事業所を探すことが大切です。実際に通う利用者自身の意向はもちろんですが、預ける家族の立場としても信頼できる施設でないと安心して任せることはできません。
まずは担当のケアマネジャーに利用目的や希望を具体的に伝えて複数の候補を提示してもらい、そこから厳選する方法がおすすめです。とくに事業所を探すときに意識してチェックしてほしいポイントは、以下の通りです。
- 人員体制や設備は整っているか
- サービス内容は希望に合っているか
- 施設の雰囲気はよいか
- スタッフの対応は適切か
- 自宅は送迎が可能なエリアになっているか
- 料金は無理なく支払えるか

デイサービスを選ぶときに最も重要な点は、設備や職員体制・サービス内容が希望に沿うものになっているかどうかです。デイサービスを利用する目的は、「入浴」「他者との交流」「機能訓練」など十人十色。たとえば自力で立ち上がることができなくなって自宅で入浴できなくなった方がデイサービスを利用する場合、介護度が高くても入浴できる設備が整っているか、個別浴かそうでないかなども聞いておくとよいでしょう。また、本人はリハビリよりも「たくさん友人を作りたい・ワイワイ楽しく過ごしたい」と考えているのに家族の希望を優先して機能訓練特化型デイを利用しても、「あそこのデイは通っても全然面白くない」と通ってくれなくなるでしょう。逆に身体機能の維持向上意欲が高い人であれば、専門的な運動器具やリハビリの専門職が在籍しているデイサービスを利用すると効果的です。
また、施設の雰囲気やスタッフ対応の善し悪しも重要です。デイサービスは家庭的な雰囲気の事業所から接遇やホスピタリティを重視した施設まで、多種多様です。今までの生活習慣や考え方・性格によっても適した事業所は異なります。ある程度目星をつけたら自宅は送迎可能なエリアになっているか・料金は無理なく支払えるかも確認しておきましょう。
このようにデイサービスを選ぶ基準は金額だけではありません。
最終的には見学や体験利用をしたうえで決めるようにするとよいでしょう。
デイサービスは介護保険施設のなかでも数が多いので、素人だけで適した事業所を見つけることは難しいかもしれません。「近いから」「みんなあそこに行ってるから」といった理由で安易に選ぶのではなく、ケアマネジャーなどの専門家から利用する目的や希望するサービス内容に適合する施設を紹介してもらうと安心です。
今回紹介した費用に関してもそのひとつ。長期的な利用を考えて、一か月どのくらいの費用負担なら問題ないかを考え、デイサービスを選択するようにしましょう。
参考文献
*1.厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第180回資料1 P1~7、17、30
*2.厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要)P4~11、29
*5.山形県鶴岡市 鶴岡市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表【R4.10.1版】
*6.「ケアマネジャー」編集部,プロとして知っておきたい!介護保険のしくみと使い方,中央法規出版株式会社,2021 P74
*7.厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 P28
*8.介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)P12~24
*9.厚生労働省 介護サービス情報公表システム 公表されている介護サービスについて
*11.いわき市 介護予防・日常生活支援総合事業報酬体系見直しに係わる質問集 P3
*12.第199回 社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1 P162
*13.厚生労働省リーフレット「高額介護サービス費の負担限度額」
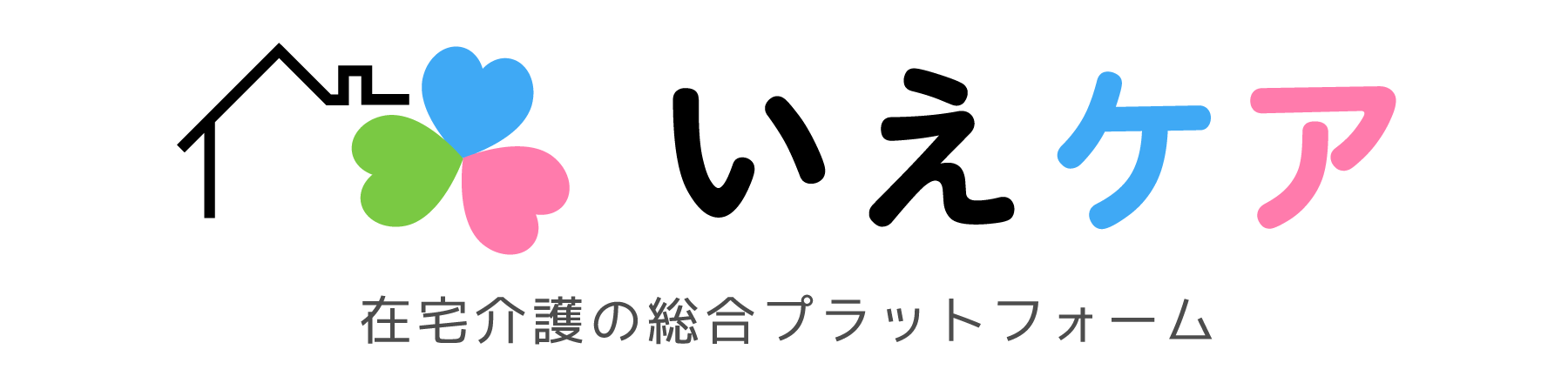




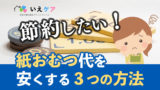






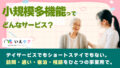
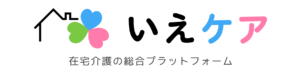


コメント